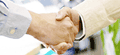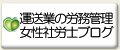おふぃま新聞 3月号
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況と第二新卒採用の活発化
厚生労働省と文部科学省の共同調査による令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(令和6年12月1日現在)によれば、大学生の就職内定率は84.3%となりました。また、短期大学は 65.2%、 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 83.1%、大学等に専修学校(専門課程)を含めると 82.0%となっています。
昨年より就職内定率は微減したものの、引き続き売り手市場が続く中、現在、新卒入社から3年以内に転職する「第二新卒」の採用意欲が増しています。エン・ジャパンが「若手人材の採用」についてアンケートを実施し、300社から回答を得た調査結果によれば、第二新卒を採用したい企業は63%と過半数を占めているそうです。
【厚生労働省「令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)を公表します」(PDFが開きます)】
【エン・ジャパン「「若手人材の採用」に関する意識調査」】
2.従業員の不祥事発覚時の初動対応
従業員による不祥事が発覚した場合、企業がその対応を誤ると、社内外からの信用を大きく損ねてしまう可能性があります。
①担当者を選任し、事実関係を把握②情報開示とコミュニケーション③被害者対応 というのが、基本的な初動対応となります。
初動対応のあとは、原因を徹底調査し、内部統制の強化や従業員教育など、再発防止に取り組むことが重要です。従業員の不祥事など考えたくないことかもしれません。ですが、誤った対応をしないよう、準備をしておくことが大切です。
3.令和7年度の雇用保険料率
厚生労働省は、令和7年度の雇用保険料率の案内を公開しました。令和5年4月〜令和7年3月までの保険料から0.1%引き下げとなりました。令和5年以来の変更となります。事業所ごとの賃金の締め日を確認し、ミスがないよう注意しましょう。
【厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」(PDFが開きます)】
4.人手不足対策に欠かせないデジタルリテラシーの向上
労働政策研究・研修機構の調査によると、人手不足対策として最も多く実施されているのが「ICTの活用による業務の効率化・自動化」で、約75%の企業が実施しています。人手不足対策の成功には既存社員のスキルアップが不可欠です。業務のデジタル化が進む中、社員のICTリテラシー、さらにはより視野の広い「デジタルリテラシー」の向上は企業の競争力強化に直結します。
一方で、調査結果からは、求人募集時の賃上げや採用方法の多様化、高齢者・女性・外国人材の積極的な登用も、人手不足対策として重要なポイントであることがわかります。これらに関する制度整備も、企業が勝ち残っていくためには必要な取組みでしょう。
【独立行政法人労働政策研究・研修機構「人手不足とその対応に係る調査(事業所調査)―小売・サービス事業所を対象として―」】
5.20代・30代のビジネスパーソン900人に聞いた「入社後ギャップ」〜エン・ジャパン調査より
この調査によると、入社後ギャップを感じたことがある方に、「想定より良かったギャップ」を伺うと、上位は「職場の雰囲気」(40%)、「仕事内容」(31%)。「想定より悪かったギャップ」でも、「仕事内容」(39%)、「職場の雰囲気」(38%)が上位に並びました。入社後ギャップを感じたことがある方に「ギャップが原因で転職したことはありますか?」と伺うと、34%が「転職したことがある」、33%が「転職はしていないが、転職活動をしたことはある」と回答しました。
【エン・ジャパン「20代・30代のビジネスパーソン900人に聞いた「入社後ギャップ」調査:『AMBI』ユーザーアンケート」】
6.外国人労働者数が約230万人と過去最多を更新〜厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」より
厚生労働省の発表によると、日本で働く外国人は2024年10月末時点で前年と比べ12.4%増えて、230万2,587人に上り、過去最多を更新しました。人手不足を背景に、企業が外国人の採用を強化しています。
【厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」】
コラム
会社の取組を評価する制度として、認定制度があります。
厚生労働省には、①従業員の子育支援(くるみん)、女性従業員の活躍支援(えるぼし)、若者の採用・育成に積極(ユースエール)があります。
認定制度には税金の優遇措置もありますので、認定取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
by office-matsumoto | 2025-03-01